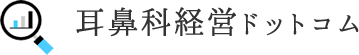耳鼻科経営におけるリンゲルマン効果(社会的手抜き)への対策
人数が増えれば増えるほど、1人当たりの発揮する力が減少...原因と対策

私たち株式会社クレドメディカルは、医療機関に特化したコンサルティング会社として、開業後の継続的な発展と安定した経営をサポートしています。
診療効率の向上、集患対策、スタッフの教育や採用など、医院経営に関わるさまざまな領域でご支援を行っておりますが、中でも「人が足りない」「うまく回らない」「採用してもすぐ辞めてしまう」といった、採用に関するお悩みを先生方からよく伺います。
人手不足が深刻化する中、募集をかけてもなかなか採用につながらないケースも増えています。
そのような状況下では、限られた人材の力をいかに引き出すかが、ますます重要になってきています。
もしかしたら、先生の知らない部分で手を抜いたり惰性で仕事をしていることにより人手不足の状態に陥っているかもしれません。
今回は、そんな組織における人の特性であるリンゲルマン効果についてお伝えします。
これは、フランスの農学者であるマクシミリアン・リンゲルマンにより提唱された、人間は集団の中で共同作業を行う際に無意識に手を抜いてしまうという理論で「社会的手抜き」とも呼ばれており、集団人数が増えると一人当たりの業務遂行量が減少するというものです。
この理論を実証するための有名な実験として、綱引きがあります。
この実験の結果は、1人の全力の力を100%とした時
・2人の場合 93%
・3人の場合 85%
・4人の場合 77%
・5人の場合 70%
と人数が増えれば増えるほど1人当たりの発揮する力が減少したという結果でした。
耳鼻咽喉科の場合、クラークや事前問診係、アフターカウンセリング係などの新しい役割をスタッフに与え、なおかつドクターが行っていた業務の移譲がない限りは、過剰にスタッフを配置しても診療効率は上がらず、むしろ人が増えた影響でスタッフ一人あたりの業務量(生産性)が減ってしまうことになります。
このような状態では患者さんの満足度も特段上がるわけではなく、「ゆっくりと仕事をするスタッフ」が増えるだけの結果となります。
このようにリンゲルマン効果は、スタッフの人数が増えれば増える程一人に対しての注目度や期待度が下がって余計に手抜きが発生しやすい状況に陥ることを指します。
やる気のあるスタッフでも周りの状況に合わせて徐々にモチベーションが下がっていき、最悪の場合には離職に繋がり、残ったスタッフは更にモチベーションが低下するという悪循環に陥る可能性もあります。
ですので、リンゲルマン効果を起こさないためにも原因を知り、それに対する対策が必要です。
それでは、リンゲルマン効果が起きる原因と対策についてご説明します。
●当事者意識の欠如と集団における同調行動
人数が増え、一人当たりの責任が少なくなると「誰かがやってくれるだろう」という考えが無意識に起きます。
また、集団になると自分の意思にそぐわないことでも同調圧力によって、周囲の言動に合わせて行動してしまいます。
この当事者意識の欠如と集団における同調行動への対策として、医院としてのあるべき姿である目標を設定し、スタッフ全員が共有できるようにする必要があります。
そして重要なのが、その目標を達成するための「役割」を明確にし、その上で「役割ごとの担当者まで決定する」ことで、「誰かがやってくれるだろう」という意識をなくすことです。
●コミュニケーション不足
コミュニケーションが取れていないと集団への帰属意識が醸成されず、疎外感から手を抜いてしまうというケースがあります。
しかし、こうした手抜きは必ずしも意図して行っているわけではなく、無意識に行っている場合もあり、対策を講じる必要があります。
コミュニケーション不足を解決するためにおすすめなのが、個別面談です。
リーダースタッフがいる医院であれば、リーダーとスタッフとの個別面談を定期的に設けて、目標の進捗確認や医院全体としての取り組みや困っていることを共有したり、業務に対してのフィードバックを各スタッフに行うことで、無関心や無責任な言動を抑制することができます。
ただし、適切なフィードバックをするためには、成果や貢献度を評価できる評価基準が必要です。
例えば、
・ひと月で平均的に延べ2000人以上の来院患者数があるクリニックでは、1か月で2000個のポケットティッシュを配布する
・医院の公式LINEのお友達登録者数を1年間で1,000人以上増やす
など具体的な評価項目を入れるのも有用です。
人員不足で困られている医院はもちろん、現在は余裕のある医院でもリンゲルマン効果によりスタッフのポテンシャルが落ちていないか今一度ご確認ください。
弊社クレドメディカルでは今回のような耳鼻咽喉科医院経営に関する内容の他、花粉症シーズンの乗り切り方や、診療報酬に関する重要なお知らせなども随時お届けしております。是非メールマガジンのご登録をお願いいたします。
また、スタッフの募集・採用から評価制度の導入、個別面談の対応まで、幅広いご支援を承っておりますので、ご質問やご依頼がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
本コラムが、耳鼻咽喉科医院の経営に少しでもお役立ていただけましたら幸いです。