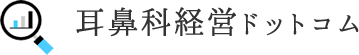採用という未来への投資
医院経営における採用戦略のポイント

クリニック経営において、「採用」は永遠の課題の一つです。
特に、電子カルテを導入しているクリニックでは、ITリテラシーの高い若手スタッフの確保がますます重要になっています。
本記事では、優秀な人材を確保するための効果的な採用戦略についてご紹介します。
1. 採用活動の4ステップ
採用活動は以下の4つのステップに分けられます。
・募集
・採用
・教育
・評価
その中で、「募集」の部分について一昔前までは、ハローワークや新聞折り込みの求人情報チラシ、都市部においてはフリーペーパーなどが主流でしたが、最近ではWEBによる求人は当たり前になりました。
しかし、上記のような媒体に頼らず優秀な人材を集めている耳鼻咽喉科医院があります。
そのような医院は、
1) ホームページ、ブログ
2) 採用ターゲットに応じた求人票の送付
を効果的に用いて採用を行われています。
これまで医院の広報としての役割だけだったホームページサイトにスタッフ採用だけを重点的に記載したページを作成することで本体のホームページサイトの充実と併せ、医院の診療方針やスタンスに共感した方が応募してくる仕組みを作成する、という手法です。
「そうか、ホームページにスタッフ募集欄をつくれば良いのか」と思われますが、勤務時間や給与などの募集要項を載せておけば良いというような簡単なものではありません。
たとえば医療事務であれば
① 自院の医療事務はどのような仕事をする仕事なのか?
② どのような人材が医療事務として適しているのか?
院長が医療事務の人間に期待する役割はどのようなものなのか?
③ 実際に働いている医療事務のスタッフのコメント
(できれば複数、顔写真や似顔絵があれば尚よい)
④ 働かれている方の1日の勤務スケジュール見本
上記の内容を一つ一つ記載するのがおすすめです。
また、その時に応募者が思うことは「スタッフのコメントを書いていて、何かよさそうな事を書いているけれど、本当だろうか?」という疑心です。
それを安心に変える存在こそが、スタッフによるブログです。
週に1度なり定期的にスタッフが更新しているブログはそこで働いている人間をイメージする一番の手段です。
特に最近では、意識の高い方はまずはホームページ、あるいはブログをチェックしてその組織の人間関係が良いものであるかを確認してから募集をする傾向にあります。
2)の採用ターゲットに応じた求人票の送付は、大学、医療専門学校、高校など各医院が欲しいターゲットに合わせ、その就職課や教務課に対して直接求人票を送付するものです。
こちらは個別に求人票を手配する必要があるため、かなり手間のかかる作業です。
しかも新卒を募集することになるので、面接、採用を行ってもすぐに入職してくれるわけではありません。
ちなみにですが、上記でお話しした
1)ホームページ、ブログ
2)採用ターゲットに応じた求人票の送付
はそれぞれ独立した採用媒体ではありません。
1)と2)を双方積極的に取り組むことで、求人票を送られた学校の学生が、さらにホームページやブログを呼んで共感し、応募してくる、という流れが作られることになります。
ですので、優秀な方を集めたい方は、双方に取り組んで頂くことが望ましいといえます。
勿論、優秀な方を見極めるには、先ほどの人事4ステップのうちの「採用」の部分についても体系立てて進めてゆく必要があります。
採用とは募集をかけて以降、履歴書が届いて選考を行い、採用通知を出すまでの一連の流れをいいますが、この採用プロセスの中で、耳鼻咽喉科医院にとって大切なことをまずは2点ほどお伝えしたいと思います。
①良い採用は院長が採用のプロではないことを認識することから
②相対的評価ではなく、絶対評価で採用は行う
以下、順にお伝えしたいと思います。
先生方は耳鼻咽喉科のプロフェッショナルであり、決して採用のプロではありません。
1年間毎週のように面接を行っているならともかく、年に数回、場合によっては数年ぶりに面接をされる場合、面接官としての技量は決して高いとはいえないことが多いようです。
結果として、
a.単に面接の際に愛想の良さそうな子
b.以前耳鼻咽喉科で働いていた経験のある方
c.(外見が)自分の好みのタイプの方
d.たまたま履歴書の趣味の欄などで話が盛り上がった方
上記のような場当たり的な要素で選んでしまいがちです。
c.などは論外ですが、b.などは即戦力として役立つではないか?
という意見もあろうかと思います。
その点は確かにその通りなのですが、他院での経験のある方はしっかりと人柄を見極めた上で採用しないと、他院での知識・ルールが頭から離れず、自院のやり方に反発したり、対応できない。
耳鼻咽喉科の経験といっても口ばかりで何もできない場合があるといったリスクを秘めています。
そのため選考の際には以下の判断基準でご判断ください。
・正しい仕事観を持っている
(単なるお金稼ぎ目的だけの方はNG)
・自分が知らないことを受け入れる素直さを持っている
・読み書きの基礎能力に加え、機転を利かせる力を持っている
・医療機関で働くに相応しい、優しさや包容力がある
・今までの人生で何かに打ち込み、やり遂げた経験がある
「そんなことわかっているけど、そんな人はなかなか来ないよ」と思われているかも知れません。
無論、良い人を集めるには募集の段階でいかに多くの候補者を集められるかにかかっているのですが、この採用の段階で重要なのは、
「上記の要素を問うような質問をしっかりと面接の場で行っているか?」
ということです。
仕事観を問う質問、素直さを問う質問、読み書きの基礎能力を測る試験機転が効くかを測る質問、これまでに打ち込んだ取り組みの有無を問う質問などです。
例えば
『私は〇〇な人間です』の○○に当てはまるものを1分以内に可能な限り沢山挙げてください』
上記はおそらく用意していないであろう問いに対していかに機転が効くかを測る質問です。
先生方においては、「自分は採用のプロでは無い」と認識した上で直感だけを頼りにせずに、聞くべき質問を予めクリニックで定め、場合によっては事務長やスタッフなどにも立ち会ってもらい、なるべく複数の面接官の下で採用を進められることをお勧め致します。
それだけ採用のプロセスは今後取り返しのつかない重要なものであると言えるでしょう。
②相対的評価ではなく、絶対評価で採用は行う
多くの耳鼻咽喉科医院の場合、募集媒体から面接に来られた方の中で良いと思った方から順番に採用をするケースが殆どだと思います。
人材募集が、「欠員が生じた際の補充」が主目的である場合が多いためやむを得ない面もありますが、できればこれも止めて頂きたいのです。
理由は単純です。
5人の応募の母集団があり、各自に10点満点で評価をつけるとして、場合によっては評価が「10」の方が5人中3人いる場合もあれば、評価が「4」の方が1人でそれ以外の4人は全て「3以下」の場合もある為です。
前者であれば、贅沢に評価「10」の方の中から選ぶことができますが、後者の場合ですと欠員の補充だからといって無理やり「4」の方を選び、入職後に教育を施してもなかなか成長しなかったり、仕事観がずれているために周りに悪影響を与えた末に退職するケースさえあります。
よって、その母集団の中から一番良い方を当たり前のように選ぶのではなく、院内で定めた一定基準を超えた方から選ぶ、絶対評価基準での採用こそが失敗の少ない採用方法であるといます。
「しかし、せっかく募集を出したのに・・・」
「人が足りないので贅沢も言ってられないよ・・・」
と思われるお気持ちも重々わかります。
ですが短期的視点ではなく長期的視点で医院経営を考えた時、上記採用方法の意義がご理解いただけるものと思います。
今後、それぞれの医院の採用の基準点を決めて頂き、問うべき質問を統一した上で、絶対評価方式での採用スタイルが定着させることに是非チャレンジしてみてください。
そのスタイルが定着すれば、より優秀な方に働いて頂ける可能性が高くなるかと思います。
最後に一点、付け加えさせて頂くなら、良い人材を採用するための募集にかけるコストは出し惜しみなく投資をして頂いたほうが、結果として良い採用ができる確率が高まり、医院にもたらす利益は大きくなるように思います。
一度採用をしてしまうと、簡単には人材は入れ替えられません。
人材はモノではありませんが、「安物買いの銭失い」にならぬよう、しっかりと計画を立てて採用を行ってください。
本コラムが、耳鼻咽喉科医院経営の一助となれば幸いです。