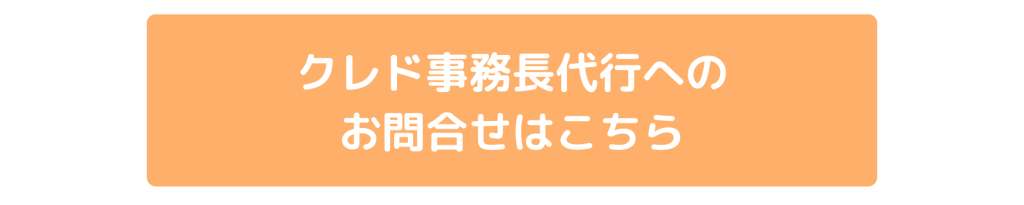スタッフの有給管理はどのように行うべき?【クレド事務長代行】
スタッフの有給管理は意外と煩雑な業務
スタッフ数が増えてくると、個別対応の求められる有給休暇の管理が一気に煩雑になります。
「誰が何日有給を残しているのか分からない」
「申請が重なって調整ができない」
「管理表の更新が面倒で、いつの間にか把握できなくなっている」
こうしたお悩みを抱えていらっしゃる院長先生も少なくないでしょう。
有給はスタッフにとっての権利ですが、クリニックの診療体制に影響を及ぼさないよう運用上の注意が必要です。
特に複数のスタッフで有給希望日が重ならないよう調整する必要があるため、有給の残日数や取得希望日が見える化されていることが重要です。
一方で、法律に沿った方法で厳密に管理しようとすると、手間や確認作業がかえって増え、現場の負担になってしまうケースもあります。
では、実際のクリニックではどのように有給管理を進めていくことが必要でしょうか?代表的な2つの運用方法について、それぞれの特徴と注意点をご紹介します。
有給付与に関する二つの考え方
有給付与の方法には「入社日に基づく付与(法定どおり)」と「日を指定して一律で付与する方法(斉一的取扱い)」の2パターンがあります。それぞれの特徴と注意点を押さえておくことが、スムーズな管理運用の鍵となるでしょう。
入社日にもとづく付与方法とその特徴
法律上の原則に則り、スタッフの入社月を基準に個別で有給を付与する方法です。最も法的に正確で、スタッフごとの在籍期間に応じた運用が可能です。
【メリット】
・法定ルールに忠実で、制度的な整合性が高い
・入社時期にかかわらず、スタッフに対して公平な対応が可能
・労働基準監督署からの指摘を受けにくい
【デメリット】
・管理が煩雑になりやすく、スタッフごとのスケジュールを都度把握・更新する必要がある
・担当者の負担が大きくなり、抜け漏れや計算ミスのリスクが増える
日を指定(斉一的取扱い)した付与方法とその特徴
「4月1日に全スタッフへ一斉付与する」など、付与タイミングをクリニックで統一する方法です。実務的には有給の管理がしやすくなりますが、注意点も多いので導入の際には社労士と相談をしていただく方がよいでしょう。
【メリット】
・スケジュール管理がしやすく、台帳更新やシステム入力の負担が軽減される
・スタッフ同士の有給残日数の比較がしやすく、調整もスムーズ
【デメリット】
・入社タイミングによっては、付与日数に差が生じるなどの不公平感が生まれる可能性がある
・法定基準とのズレを放置すると、指摘やトラブルにつながる恐れがある
・クリニック独自のルールを設定する場合は、就業規則と有給運用ルールとの整合性の確認が必須
【特に注意が必要となる点】
1)就業規則への明記が必要
10名以上のスタッフが在籍している場合は、就業規則の変更と労働基準監督署への届け出が必要になります。10名未満でも、就業規則に準じたルールを整え、スタッフに周知することが望ましいでしょう。
2)基準日の設定に注意が必要
法律上は「入社日から6か月後」に有給休暇を付与することが義務づけられています。したがって、それより後ろ倒しで一律の付与日を設定することはできません。
(例:8月入社のスタッフの初回付与日が一律付与日の4月1日になる/本来は2月1日が有給付与日)
もし一律付与日が入社日から6か月経過後より遅くなる場合には、入社時点で有給休暇とは別に特別休暇を付与するなどの対応が必要となります。
3)スタッフが本来取得できるはずの有給日数を下回らないよう注意が必要
付与のタイミングを統一しても、結果として「本来付与すべき日数より少ない状態」となってしまうと、労働基準法違反と見なされる可能性があります。形式ではなく、実質的な付与内容が重要です。
まとめ
有給の付与方法には、「入社日に基づく付与(法定どおり)」と「日を指定して一律で付与する方法(斉一的取扱い)」の2種類があります。法的整合性を重視するなら入社日ベース、実務の簡素化を図るなら一律付与と、それぞれにメリットとデメリットがあります。
大切なのは「どちらの方法が正解か」ではなく「貴院にとって現実的に運用しやすい仕組みかどうか」という視点です。そのためには、就業規則との整合性や、スタッフへの周知・管理体制の構築といった実際に機能するルールづくりが欠かせません。
「スタッフの有給管理を誰かに任せたい」
「有給申請・承認フローを整えたい」
「就業規則の見直しを機に、ルールと実務を整えたい」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度クレド事務長代行にご相談ください。貴院の体制や課題に合わせ、実務に根差した最適な管理方法を一緒に構築いたします。