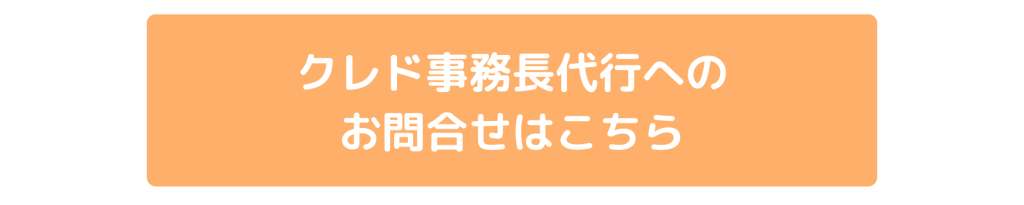電子処方箋、導入後に見えてくる「運用の壁」とは?【クレド事務長代行】
電子処方箋、制度は整ったものの運用に課題も
電子処方箋制度は、薬剤情報の一元管理や重複投薬の防止といった観点から制度設計されており、医療の安全性と効率化を推進する取り組みのひとつです。しかし、導入の背景としては「医療DX推進体制整備加算の算定要件だから」「補助金が出ている今のうちに整えておきたい」といった理由が多くを占めています。
その結果、制度としての整備は進み始めている一方で、実際に運用を始めた院長先生やスタッフからは「操作に慣れておらず、電子カルテ上のどのボタンで何ができるのか把握できていない」「処方名の表記が従来の呼び方と異なり、どれを選べばいいかわからない」など、操作面での戸惑いの声が多く聞かれます。制度上の整備と現場の実態にギャップがあることで「導入済みだが現場では機能していない」というクリニックは少なくありません。
電子処方箋、3つの大きな「運用の壁」
電子処方箋の仕組みは一見シンプルですが、実際に診療の中で使い始めてみると様々な運用の壁があり「使用できる環境にはあるが活用していない」という状況に陥りやすいのが現実です。代表的な運用課題には以下のようなものがあります。
名称変更による混乱
電子処方箋では、処方名や処置名を電子処方箋仕様に表記に統一する必要があります。そのため現場のスタッフが従来の表記との違いに戸惑い、処方を検索・選択する際に時間を要する場面が増加します。結果として、確認・変換・追記といった工程が発生し、診療効率に影響を及ぼすこともあります。
重複処方チェックによる待機時間
電子処方箋の重要な機能のひとつに、過去の薬剤履歴と照合するオンラインチェックがありますが、これには10〜20秒程度の待機時間が発生します。読み込みが完了するまで診療の手を止めざるを得ず、診療のテンポが崩れる原因にもなりかねません。
確認フローの煩雑化
薬局側からの疑義照会がシステム経由で届くケースも多く、改めて処方を確認・修正する必要が出てくることがあります。また、医療機関と薬局で使用しているシステムが異なる場合、情報のタイムラグや送受信エラーが発生し、最終的には電話での確認に頼るといった場面も。こうした繰り返しがスタッフの「結局、紙で処方箋を発行したほうが業務の手間が少ない」という声につながっています。
「わかる」から「使いこなせる」へ
クレド事務長代行では「電子処方箋を導入したものの、スタッフがなかなか使いこなせない」といったご相談を多くいただいています。実際ご契約いただいているクライアントのほとんどで「システムのマニュアルだけではスタッフの理解が及ばず、業務に活かしきれない」との声が挙がっており、クレド事務長代行としても対応を行っております。
電子処方箋における混乱の多くは、制度の理解不足ではなく「現場で起こりうるケースを想定した準備不足」によるものです。
そのため、以下のような運用時の具体的な対処方法まで含めた実践的なマニュアルの整備が不可欠になります。
・待機時間発生時の対応方法
・異なる名称の処方をどう選び・記録するか
・システムトラブル時に薬局とどう連携するか
こうした「運用時に起こりがちな”つまずき”」にあらかじめ備えておくことが、スタッフの不安軽減やスムーズな定着に繋がります。
まとめ
電子処方箋は、発行の体制を整えるだけで完結するものではありません。クリニックの現場でしっかり活用されてこそ、その効果が発揮されます。
「電子処方箋の運用が不安定で、現場に負担がかかっている」
「制度には対応しているはずなのに、実際の運用がうまくいかない」
こうしたお悩みは、電子処方箋に限らず、採用・届出・業務整理などクリニック運営全般に共通するものです。現場で感じる「ちょっと困った」を解決するには、制度やシステムだけでなく現場で機能する仕組みを整えることが欠かせません。
クレド事務長代行では、電子処方箋を含む日々の業務の「定着支援」はもちろん、採用や届出対応、業務効率化の見直しまで、クリニックの運営を幅広くサポートしています。
「今のやり方が本当にベストなのか確かめたい」
「雇用までは考えていないが、業務を一部委譲したい」
そんなお悩みをお持ちの院長先生には、まずは一度お話を聞いていただくだけでも結構です。ご状況に合わせて、最適なサポート方法をご提案させていただきますのでどうぞお気軽にご相談ください。