
1.深刻化するペイハラの現状と影響
近年、医療現場において、患者さんやそのご家族からのハラスメント行為(ペイシェントハラスメント、通称ペイハラ)が深刻な問題として認識されています。
診察内容への不満から居座る、自分や家族の診察を優先するよう要求するといった理不尽な要求に留まらず、怒鳴る、体を触る、といった暴言や身体的な接触、さらには土下座や謝罪の強要、診療費の不払いや金銭補償の要求、無許可での動画撮影といった事例も報告されています。
どのようなクリニックにおいても、医療従事者が暴言や理不尽な要求等の被害に遭う可能性は決してゼロではありません。
ペイハラ行為は、被害を受けた医療従事者に強いストレスや恐怖を与え、精神的な負担が蓄積することで、休業や離職といった深刻な事態を招きかねません。
また、対応に時間を取られることで、他の患者さんの診療にも影響が出てしまう可能性があります。
2.ペイハラが発生する背景と要因
ペイハラの発生には、患者さん側の要因と医療機関側の要因が複合的に影響していると考えられます。
【患者さん側の要因】
元々の性格や家族関係、人間関係でのトラブル等が影響しているケースもあります。
また、「医療はサービス業だから患者が満足のいくサービスを提供するのが当然」といった認識や、医療に対する過度な期待や理解不足から、思うような結果が得られない場合に不満が爆発し、理不尽な行動に繋がることがあります。
【クリニック側の要因】
長い待ち時間、スタッフの説明不足やオペレーションミス、高圧的な態度、情報共有不足による認識齟齬などが、患者さんの不満や怒りを増幅させる可能性があります。
ただし、病院・クリニック側に落ち度がなくてもペイハラが発生することもあります。
3.今こそ取り組むべきペイハラ対策
医療現場を守り、安全で質の高い医療を提供するためには、組織全体でのペイハラ対策が不可欠です。
以下に、具体的な対策を3つの柱としてご紹介します。
(1)組織的な対応の強化
■ペイハラへの対応方針の作成
まず、貴院としてペイハラを断固として許さないという明確な方針を定め、それを患者さんやご家族、そして全職員に周知することが重要です。待合室や受付にペイハラ防止のポスターや注意喚起を掲示することも有効です。
■対応マニュアルの作成
マニュアルには、ペイハラの定義、具体的な事例、発生時の対応手順、役割分担、報告経路などを明記します。
特に、初期対応の重要性を強調し、エスカレートさせないための具体的な方策を盛り込みましょう。
■発生時の対応
ペイハラが発生した際には、決して一人で対応させず、複数人で冷静に対応することを原則とします。状況を正確に記録し、複数人で情報を共有することも重要です。
また、対応責任者を明確化し、組織として問題解決に取り組む姿勢を示すことが、職員の安心感に繋がります。
(2)従業員への教育・研修の徹底
作成したマニュアルに基づき、全職員に対して定期的な教育・研修を実施し、ペイハラに対する知識と対応力の向上を図りましょう。
研修では、ペイハラの定義や事例、対応の基本(冷静な対応、傾聴、毅然とした態度)などを伝えましょう。
また、患者さんとのコミュニケーションスキル向上のための研修も重要です。
丁寧な説明や共感的な対応を心がけることで、患者さんの不満や不安を軽減し、ペイハラの発生を未然に防ぐ効果も期待できます。
(3)心理的なサポート体制の整備
ペイハラを受けた職員は、心に深い傷を負う可能性があります。
そのため、相談しやすい窓口を設置し、カウンセリングなどの心理的なサポート体制を整備することが不可欠です。
4.東京都カスハラ防止条例からの示唆
2025年4月1日には、東京都で全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行される予定です。
この条例は、医療機関における患者さんからの著しい迷惑行為も対象となり得るものであり、「カスハラの一律禁止」や「事業者の責務」などが定められています。
罰則規定はありませんが、カスハラは違法であるという社会的な認識を高め、被害の減少・緩和が期待されています。
ペイハラは、医療現場で働くすべての人々の尊厳を脅かし、安全な医療提供を妨げる重大な問題です。
院長先生をはじめとする経営層が、この問題に真摯に向き合い、組織全体で対策に取り組むことが、職員の安全と健康を守り、ひいては患者さんへの質の高い医療提供に繋がります。
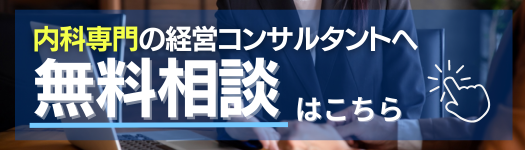
具体的なマニュアルの作成方法やスタッフへの教育方法・研修方法などは、無料の経営相談で詳しくお伝えいたします。
お気軽にご相談ください。
「内科医院専用」無料の個別質問会のご希望はコチラから
また、クレドメディカルの内科医院専用メールマガジンでは、持続可能な内科医院経営を実現するためのヒントや、組織マネジメントに関する最新の情報をお届けしています。
内科医院の成長をサポートする貴重な情報を、是非ご活用ください!
「内科医院専用」メールマガジンのご登録はコチラから



の活用.jpg)









